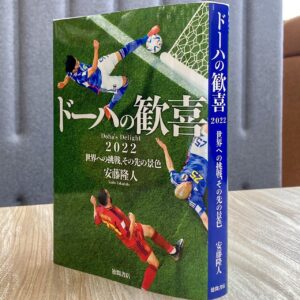- 安藤隆人さんコラム
- プロモーションビデオ
- チーム+スケジュール動画
安藤隆人さんスペシャルコラム前編
カタールW杯でドーハの歓喜をもたらしたサニックスカップ出場選手
ユース年代の本格的な開幕は4月。全国リーグである高円宮杯プレミアリーグ、地域リーグであるプリンスリーグ、そして都道府県リーグと、昨今の育成年代はリーグ戦が整備されており、このリーグ戦の幕開けがシーズンのスタートを告げる形となっている。それゆえ2月、3月は新チームが始動し、新たなシーズンに向けて強化をする重要な時期になる。特に3月は春休みに入るため、長期で遠征ができる絶好の機会。この時期は全国各地で高校サッカーやJリーグのクラブユース、街クラブなどが集まって強化試合となるフェスティバルを開催する。
そのなかにおいて、今年で21年目を迎えるサニックス杯国際ユース大会は、大会の規模や実力レベル的にも非常に高いフェスティバルとして認知されている。
開催する場所は福岡県の宗像市にあるグローバルアリーナ。ここは株式会社サニックスの創業者である宗政伸一氏が青少年のスポーツを通じた育成を理念に作られた、巨大スポーツ施設だ。天然芝の球技専用のメインスタジアムの横には陸上トラックと芝生のピッチがあり、さらに天然芝ピッチが3面連なり、その上には人工芝ピッチ1面がある。合計6面のサッカーコートが取れ、グラウンドのそばには合宿にも適した宿泊施設があり、ミーティングルームなどを完備した大きなクラブハウスもある。
この充実した設備を利用して、2003年からスタートしたのがサニックス杯国際ユース大会であった。『国際』とついているように、当初から選手たちの国際交流も狙いとして設けられた大会であり、これまでACミランユース、インテルユース、アヤックスユースなどヨーロッパの名門クラブのユースが参加したほか、U-17中国代表、U-16韓国代表、U-17ウズベキスタン代表、U-17ベトナム代表、U-17マレーシア代表など、アジアのナショナルチームも参加をする日本でも非常に稀有な大会であった。
日本からも強豪Jユース、強豪高校だけでなく、U-16日本代表、U-17日本代表が参加し、その先にあるアジア予選やU-17W杯に向けた強化に位置付けるなど、大会の規模や質は非常に高いものがあった。
私も2003年の第一回大会からずっとこのフェスティバルを取材しているが、これまで何度もハイレベルな試合を目の当たりにしてきた。これだけの規模とレベルを誇る大会だけに、数多くのスター選手がグローバルアリーナのピッチで躍動を見せてきた。
昨年11月から1か月間、中東はカタールで開催されたFIFAワールドカップカタール2022。森保一監督率いる日本代表がグループリーグでドイツとスペインという2つの優勝経験国を逆転勝ちで撃破をして『ドーハの歓喜』と呼ばれる大金星を挙げたことは記憶に新しいだろう。
日本中を熱狂の渦に巻き込んだ日本代表の主役たちも、かつてこのピッチを踏み締めていた。
初戦のドイツ戦で劇的な決勝弾を叩き込んだ浅野拓磨(ドイツ・ボーフム)は、四日市中央工業高校のエースストライカーとして2012年の大会に参加をしていた。
この大会の2か月前には第90回全国高校サッカー選手権大会において、2年生エースとして大爆発し、チームを準優勝に導くだけではなく、史上4人目の全試合ゴールを挙げて得点王の個人タイトルも手にした。
選手権で彗星の如く現れたストライカーを視察しに、会場には多くのスカウトが訪れていた。1年の時から取材をしていたが、彼がここまで注目を集めることは選手権前まではなかっただけに、これには正直驚いたことを覚えている。
「サニックスは選手権と同じようにたくさんのスカウトが来ることは知っています。ここで進路が決まる選手もいるので、僕も相当気合が入っています。もちろんそれだけではなくて、早くもリベンジの場が来たので、これで燃えないわけがないです」
大会初日に彼はこう語っていたように、相当なモチベーションでこの大会に臨んでいた。彼が言う「リベンジの場」とは、選手権決勝で延長戦の末に敗れた市立船橋高との対戦であった。
迎えた市立船橋戦、彼は気合に満ちた表情でピッチに立つと、得意のスピードを惜しげもなく発揮。ボールを持ったら迷わず縦に仕掛けると、ゴール前では冷静にシュートと質の高い判断をして、チャンスを作り出した。
ゴールこそ奪えず、チームも選手権決勝のスコアと同じ1-2で敗れたが、相手の堅守の歪みを作り、かつ正確なラストパスで周りを生かすプレーの質の高さは一級品で、ただ速い選手ではなく、「上手い選手になってきたな」という印象を受けた。
「市船が相手だったので何がなんでも勝ちたかった。良いプレーは出来たかもしれないですが、結果が決勝と同じなので、まだまだだなと感じました」
試合後、彼は悔しそうな表情を浮かべていた。そこには選手権で得点王を取ったことに対する慢心は一切なかった。
選手権での浅野は、同じ2年生のFW田村翔太(現・ヴィアティン三重)と『ダブルストライカー』として抜群の連携を見せてゴールを量産した。しかし、この大会では選手権で浅野に次ぐ6ゴールをマークした田村が、早生まれだったこともあって同じ大会に参加するU-17日本代表の方でプレーをしていた。
「翔太がいないことで自分に任される役割が増えたともいます。これまでは2人のコンビネーションでごまかせていた部分が、ごまかせなくて自分の真の力が問われている大会だと思っています」
阿吽の呼吸であるパートナーがいない中で、自分一人で何ができるか。そう考えながらプレーしていたからこそ、彼は周りからの注目に浮かれることなく地に足をつけて、グローバルアリーナのピッチに立っていた。
「僕は早生まれじゃないので(U-17日本代表に)入れないのはわかっていますが、やっぱり翔太が羨ましい気持ちもあります。僕も日本代表の青いユニフォームを着てプレーできるようになりたいです。代表はやはり僕の中で憧れであり、ならないといけないものだと思っています」
こう話していた言葉が、リオデジャネイロオリンピック、そしてカタールW杯で現実のものになっている。高校生だからどうこうではなく、年代関係なくどこまで本気で夢や目標を持って取り組み続けることができるか。大切なものを私はこの大会の彼の言葉や表情から教えてもらったことが印象的だった。

カタールW杯では決勝トーナメント初戦のクロアチア戦の直前に体調不良になりベンチ入りできずと不完全燃焼に終わってしまった久保建英だが、今彼はスペインリーグで絶好調をキープしている。W杯前の2022年7月にレアル・マドリードからレアル・ソシエダに完全移籍をした彼は、新天地で持ち前の個人技とラストプレーやフィニッシュの正確性を発揮。今季は4ゴールをマークし、レアル・ソシエダの攻撃の中枢となっている。
久保がこの大会に出場をしたのは2016年のこと。当時、15歳だった久保は、この前年にスペインから帰国したばかり。U-17W杯アジア最終予選となるAFCU-16選手権を控えたU-17日本代表の一員としてグローバルアリーナのピッチに立った。
当時、中学2年生だった久保はテレビなどで取り上げられており、この大会での注目度も凄まじかった。
グループリーグ開幕戦のU-17ウズベキスタン代表戦に途中出場をすると、第2戦のU-17韓国高校連盟選抜戦において、鮮やかなハーフボレーを突き刺したことで、より話題が膨らんだ彼だったが、高校生とのフィジカルの差はやはり大きく、激しいコンタクトに苦戦していた。
それでもファーストタッチのうまさとボールを持ってからの身のこなしと技術は、中学2年生とは思えないほどレベルが高く、群を抜いている。フィジカル負けをして倒されている久保の姿を見て、U-17日本代表を率いていた森山佳郎監督が口にしていた言葉が印象に残った。
「もう『技術で上回れば良い』という考えは捨てた方が良い。例えばイングランドだったら、U-15とU-18では、あっという間に差が付く。将来、自分より速くて、強くて、上手い海外の選手と互角に渡り合うためには、13〜15歳から(どんな環境下でも戦える選手の育成を)始めないと、取り残されて行く」
まさにこの時、久保はその渦中にいた。森山監督が彼に対して特別扱いをせず、厳しい要求をし、久保もまたその意図を理解して応えようとする姿を見て、久保の持っているポテンシャルと精神的な強さをひしひしと感じることができた。
「代表のエンブレムを背負っているし、毎日一生懸命やっています。でも、どの相手もフィジカルが強い中で、真っ向勝負で勝てないときもある。ボールの置き所など考えながらプレーすることを意識しています」
試合をこなすごとに力強さを増していく久保。U-17日本代表も準決勝で青森山田、決勝で東福岡高を下して優勝を飾った。
カタールW杯でも、スペインでも屈強なフィジカルの相手を翻弄していく技術とキレを見せる彼の若き日の成長を感じられる貴重な経験の1つであった。

久保がプレーした1年前の2015年の大会には、2人のカタールW杯戦士がU-17日本代表の一員として出場をしていた。
世界最高峰のリーグと言われるプレミアリーグの名門であり、今季首位を走っているアーセナルでプレーをし、カタールW杯でも守備の要としてプレーしたCB冨安健洋にとって、この大会は日本代表として韓国にリベンジをする場であった。
これは筆者が今年2月に出版をした『ドーハの歓喜 2022世界への挑戦、その先の景色』(徳間書店)でも描いたのだが、この大会の前年の9月に冨安はタイで開催された、AFCU-16選手権にU-16日本代表の守備の要として出場をしていた。
世界の切符が懸かった重要な準々決勝・U-16韓国代表戦で、彼は相手の絶対的エースに完全に力で上回られての2失点を喫し、0−2の完敗。U-17W杯の切符を失うという苦い経験をしていた。
あの完敗劇から約半年。年齢が一つ上がったU-17日本代表として、冨安は開幕戦でU-17韓国代表と激突した。メインスタンドで行われたこの試合は、激しい雨の中で行われた。
「韓国の狙いは分かっているので、それを絶対にやらせないことを意識した」と、冨安は所々に水溜りのできたピッチ上でも相手のロングボールに対して、空中戦の強さとセカンドボール回収のうまさ、カバーリングの正確性などを披露した。
結果は1-1のドローで、勝ち点を決めるPK戦では敗れてしまったが、相当な気合いを持ってこの試合に臨んでいた冨安。試合後に話を聞くと、彼は決意をにじませながらこう答えた。
「(AFC U-16選手権の韓国戦は)悔しさしかありません。相手のエースに一人目が抜かれたときに、自分が行くか行かないか迷った瞬間に、縦を空けてしまい、そのまま突破を許した。その瞬間は今でも焼きついていて、その反省から今は次にボールがどこに来るか、相手がどこに仕掛けてくるかをしっかりと予測をして奪いきれるかなど細部に拘ってやっています」
彼はあの敗戦から身にしみて学んだことを、この試合でしっかりと表現していた。このやりとりの中で、私は「彼はマイナスな経験をしっかりと受け入れ、分析して、正しい方向に努力ができる選手なんだ」と確信することができた。カタールで日本の試合を取材している時も、あの雨の中で気迫と共に成長を示したプレーをしていた姿が一瞬思い浮かんだほど、印象的な試合と試合後のコメントであった。
余談だが、この時、彼の身長がタイで見た時よりもさらに伸びていることに気づき、そこに触れると、「そうなんです。まだ伸びています」と笑っていたことも印象的なエピソードだった。

現在、ドイツ・ブンデスリーガのシュツットガルトで遠藤航と共に活躍する伊藤洋輝は、ボランチとして、現在横浜F・マリノスで主軸として活躍する渡辺皓太とダブルボランチを組んで、攻守の中枢を担っていた。
U-17韓国代表戦では冨安と共に188cmの高さを生かした空中戦と、ぬかるんだピッチをものともしない正確な左足のキックで攻撃のテンポを生み出していた。
前線にはアルビレックス新潟で絶対的な存在となっている伊藤涼太郎、サガン鳥栖でプレーするスピードスターの岩崎悠人がおり、伊藤の絶妙なパス出しからゴールに迫る攻撃は迫力があった。

このようにカタールW杯で躍動した選手たちも、サニックス杯国際ユース大会で貴重な経験を積み、成長を遂げた過去があった。後編では今、Jリーグで活躍し、チームの主軸になったり、将来の日本代表選手として期待されている選手たちのこの大会での様子やエピソードを紹介していきたい。
安藤隆人さんスペシャルコラム後編
これから注目の選手たちとサニックス杯
サニックス杯国際ユース大会の振り返り。前編ではカタールW杯選手たちの高校時代を振り返ったが、後編では今、Jリーグで活躍し、チームの主軸になったり、将来の日本代表選手として期待されている選手たちのこの大会での様子やエピソードを紹介していきたい。
2009年の第7回大会では東京ヴェルディユースのサッカーの質が非常に高かった。当時の東京Vユースには高木俊幸と善朗の高木兄弟、三竿雄斗らがいた。俊幸と善朗のコンビネーションはさすが兄弟と思わせるほど絶妙で、市立船橋高戦では彼ら2人のコンビネーションで堅守・市船を翻弄し、当時フィニッシャーとしても優秀だった三竿がゴールを決めて2-1の勝利を挙げるなど、彼らの連携は今でも強烈に印象残っている。

2015年の第13回大会では、現在はJ1王者の横浜Fマリノスの中盤に君臨する渡辺皓太、今年からJ1のサガン鳥栖に移籍をした河原創、横浜FMで昨年にJ1リーグの年間最優秀選手賞に輝き、今年からスコットランド1部のセルティックに移籍をした岩田智輝、清水エスパルスに所属する神谷優太の4人に注目をしていた。
東京Vユース所属だった渡辺はこの大会ではU-17日本代表の一員としてプレー。ボランチとしてセカンドボールへの反応が秀逸で、素早くボールを拾ってはドリブルで一気に運んだり、絶妙なタイミングで攻撃のスイッチとなる縦パスを入れたりと、1人で攻撃のリズムを作り出していた。
河原が所属していた大津は、当時、CB野田裕喜(現・モンテディオ山形)、FW一美和哉(現・京都サンガ)、MF杉山直宏(現・ガンバ大阪)らが揃う全国屈指の実力を持ったチームだった。その中で河原は168cmと小柄ながら豊富な運動量と球際の強さを見せて、どこにでも顔を出してボールを奪う存在だった。スペースが空いたと思うと、直ぐに河原が走り込んできて、ボールを受けた相手に激しく寄せている。しかも簡単に交わされることがなく、どれだけフェイントで揺さぶっても文字通り食らいつくようにマークを離さない。彼のずば抜けた献身性は見ていて非常に面白かったし、魅力的だった。

河原は福岡大を経て、2020年から2022年までロアッソ熊本でプレーし、J3からJ2昇格を経験。昨年はJ1昇格あと一歩のところまで大躍進をした熊本において、全試合フルタイム出場を果たすなど、不動の攻守の要になったことで、前述した通り今年からJ1の鳥栖に個人昇格を果たしている。
大分トリニータU-18に所属していた岩田は見に行く度にポジションが違う選手だった。彼が1、2年生の時は主にサイドハーフとFWがメインで、右サイドから強烈な突破を仕掛けたかと思えば、FWでは身体を張ったポストプレーと一瞬の抜け出しでゴールに迫る。この大会ではボランチ起用をされていて驚いたことを覚えている。
どんなプレーを見せてくれるのかワクワクして見ていると、彼が繰り出したのは鮮やかなターンだった。DFラインからのボールをキュッと鋭いターンで前を向くと、正確なキックと積極的なドリブルで前にボールを運んでいく。あまりのキレと技術の高さに、磐田という選手のポテンシャルの高さをこれでもかと思い知らされた。
その後、彼はトップチームに昇格し、サイドバック、サイドハーフ、CB、ボランチをハイレベルでこなすと、J2昇格、J1昇格を経験。2021年に横浜FMに完全移籍をし、前述した通り一気にステップアップを果たした。
当時、青森山田の10番を背負って出場をした神谷にとって、このサニックス杯は『高校サッカーデビュー戦』だった。2014年の年末に彼はジュニアユースから所属をしていた東京Vユースから青森山田に転校し、新チームの10番を託されて、この大会で初お披露目となったのだった。

トップ下に君臨した神谷は、巧みなボールキープ、正確なラストパス、そして強烈なシュートと、攻撃の中軸として機能した。グループリーグ第3戦の東福岡戦では、GKの逆を突く強烈なミドルシュートを叩き込むなど、1得点1アシストの活躍。大津、東福岡、三菱養和SCユースと、今大会の最激戦グループと言われたグループBを3勝で1位通過。準決勝ではU-17日本代表を1−0で下し、決勝ではU-17韓国代表に敗れたが、堂々の準優勝に導いた。
翌2016年の第14回大会では東福岡が準優勝に輝き、この時に新2年生ながら10番を背負った福田湧矢の存在感は際立っていた。左のアタッカーとして高い突破力を披露し、サイドからのクロス、カットインからのシュートとチャンスメークからフィニッシュまでなんでもこなせる能力を見せつけた。
他にも上位には食い込めなかったが市立船橋は強烈なチームだった。1年生の時から不動のレギュラーで背番号10番を背負うMF高宇洋(現・アルビレックス新潟)が最高学年を迎え、心身ともにチームの中心となって抜群のキープ力とシュートセンスを披露。この時の市立船橋には杉岡大輝(現・湘南ベルマーレ)、原輝綺(現・グラスホッパー、スイス)、金子大毅(現・京都サンガ)真瀬拓海(現・ベガルタ仙台)など豪華メンバーが揃っており、高を中心に非常に質の高いチームだった。

福田が高校3年生になる2017年の第15回大会では、東福岡vs流通経済大柏の一戦で、福田とCB関川郁万(現・鹿島アントラーズ)のマッチアップが非常に面白かった。キャプテンマークを巻いて、前線から味方を鼓舞し、ボールを受けたら抜群のキープ力を見せる福田に対し、高校2年生になる関川が迫力満点の寄せとフィジカルの強さを見せる。
「相手が有名な選手だということは知っていたので、絶対に負けちゃいけないと思っていた」と自ら勝負を挑む形で激しいマッチアップを何度も見せた。最初は福田の身のこなしとキレにバランスを崩すなどしていたが、時間が経過するにつれてボールを奪い取るシーンも見られるようになり、戦いの質が上がっていくことが見ていて非常に楽しかった。
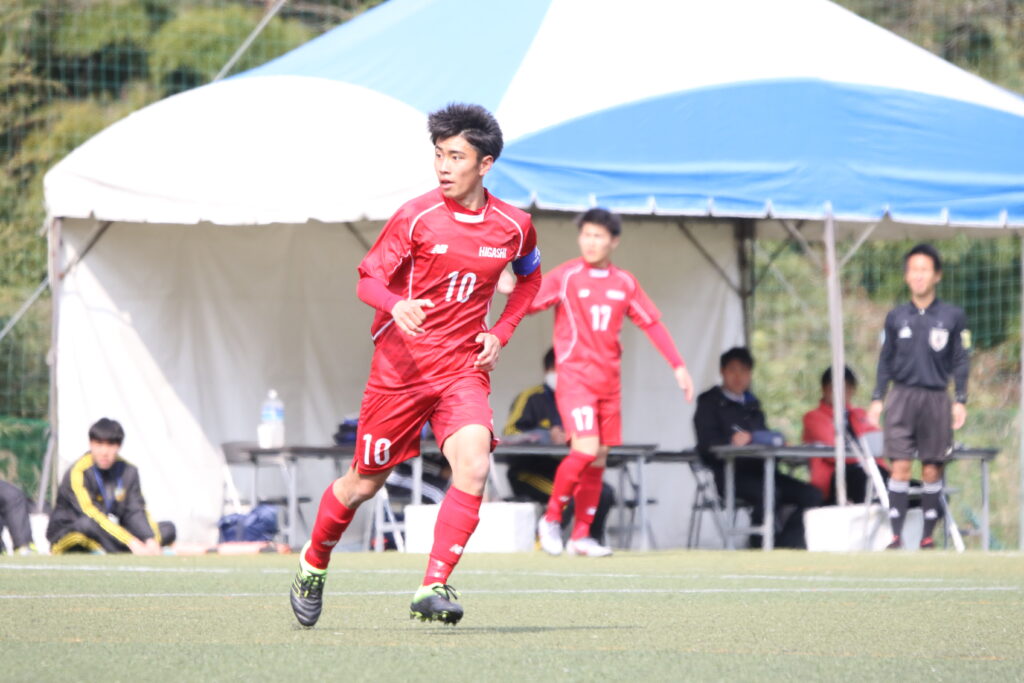
東福岡で言えば荒木遼太郎のプレーも非常に見ものだった。東福岡の10番として2019年の第17回大会に出場をした彼は、どんな体勢でもボールを持ちながら常に顔が上がっていて、次へのプレーの選択スピードが非常に早くて正確だった。トップ下からアンカーにコンバートされたばかりで、アンカーとして広範囲をカバーしながら、ボールの中継点として機能し、パスとドリブルで攻撃を牽引する。当時、視察に来ていた鹿島アントラーズのスカウトが、「ものすごく成長をしている。なんでもできるし、将来性もある」と目を輝かせていた。その後、荒木は熱烈オファーを受ける形で鹿島入りを果たし、プロ3年目の2022年から名門クラブの10番を託されている。

個人的にサニックス杯と言えば、毎年のようにタレントを抱えている前橋育英のプレーが見られるのも楽しみの1つだった。
黄色と黒の縦縞の伝統のユニフォームを身に纏った選手たちの中で、この大会でインパクトを残したと言えば、鈴木徳真、角田涼太朗の2人が浮かぶ。鈴木徳真はU-17日本代表として2014年の第12回大会に出場。ボランチとしてキャプテンマークを巻いて正確なプレーでチームの落ち着きどころとして機能。常に周りを見渡しながら正確なトラップとパスで、ほぼノーミスなプレーをやってのけるなど、堅実かつ正確なプレーはセレッソ大阪のボランチとしてプレーする今も変わっていない。
左利きのCBとして大きな注目を集めていた角田は2017年の第15回大会に出場。183cmの高さを生かした空中戦の強さと、左足の正確な長短のキックの質はずば抜けており、一発で局面を変えたり、フィニッシュまで直結するような縦パスを打ち込んだりと、能力の高さを随所に見せていた。
当時の前橋育英のDFラインは松田陸(現・ジェフユナイテッド千葉)、渡邊泰基(現・アルビレックス新潟)、後藤田亘輝(現・水戸ホーリーホック)と全員がのちのJリーガーとなり、さらに中盤には田部井涼(現・ファジアーノ岡山)、五十嵐理人(現・栃木SC)、FWには飯島陸(現・ヴァンフォーレ甲府)、室井彗佑(現・大宮アルディージャ)、宮崎鴻(現・栃木SC)など錚々たるメンバーが揃っていた。

最後にやはりサニックス杯を賑わせた大物と言えば、現在、FC東京で不動のレギュラーとして君臨し、U-20日本代表のキャプテンとしてアジアで躍動している松木玖生の存在を外せないだろう。
彼は中学生の時からサニックス杯で強烈なインパクトを与えてきた。高校最後のサニックス杯は2021年の第19回大会(第18回大会は新型コロナウィルス感染症の関係で中止)だった。
前年度から背負う10番とキャプテンマークを巻いた松木は、「チームをまとめていくのがキャプテンなので、常に周りに気を配りながら取り組みたい。難しいことですが、これを1年間実行したいなと思います」と気持ち新たに新シーズンに挑もうとしていた。
その気迫がプレーでもピッチ外での姿勢にも現れていた。ピッチ上では常に声を出し、球際も全然からの守備も誰よりも激しく、闘争心を漲らせながらやっていた。激しいプレスバックでカウンターを阻止すると、大きな雄叫びを上げ、味方が緩いプレーをすれば容赦無く叱咤した。攻撃面でもダブルボランチの一角として、爆発的なスプリントで前線まで何度も駆け上がり、FW名須川真光(現・順天堂大学)と息のあったコンビネーションを見せてゴールに迫った。
ボックスtoボックスを何度もアップダウンし、攻守において強度も精度も高いプレーを見せつける。ピッチ上での彼は獰猛かつ勝利に飢えたハンターとして、凄まじい存在感を放っていた。

「今年のテーマは『常にゴールを目指す』こと。守備をしっかりとこなしつつ、ゴール前には必ずスプリントをして入り込む。仲間への信頼度は高いですし、自分一人だけではなく、仲間と助け合いながら強度を前面に出せるチームにしていきたいと思います。今年の目標は3冠。このサニックス杯を皮切りに全開でこの1年間を戦っていきたいと思います」
グローバルアリーナのグラウンド脇でこう熱く語っていた言葉を、彼はそのまま有言実行して見せた。インターハイ、高円宮杯プレミアリーグEAST、高校選手権の3冠を達成し、2022年に鳴り物入りでFC東京に加入。クラブ史上初となる高卒ルーキーで開幕スタメンを勝ち取ると、ルーキーイヤーでリーグ31試合出場し、2ゴールをマークするなど主軸として活躍。今年は中学3年生でサニックス杯に出場したときに背負っていた7番を背負い、FC東京だけではなく、U-20日本代表、パリ五輪代表のエースとしての期待を一身に集めている。
今年で21回目を迎えるサニックス杯国際ユース大会。今回は青森山田、前橋育英、大津、東福岡、柏レイソルU-18、サガン鳥栖U-18、ヴィッセル神戸U-18と高円宮杯プレミアリーグに所属する全国トップレベルの高校、Jクラブユースに加え、U-17マレーシア代表、インドのリライアンスFヤングチャンプスU18、韓国のチェジュユナイテッドFCユースが参加。ここから羽ばたいて行った名だたるタレントたちのように、今回もハイレベルな国際大会として新たな才能の息吹を感じさせる選手と出会える大会となるはずだ。
安藤隆人プロフィール

1978年2月9日生まれ、岐阜県出身。高校、大学、Jリーグ、日本代表、海外サッカーと幅広く取材し、これまで取材で訪問した国は40を超える。サッカージャーナリスト歴は27年。
2022年カタールW杯も合計27試合を取材。
その1ヶ月間の激闘を密着取材をした『ドーハの歓喜 2022 世界への挑戦、その先の景色』(徳間書店)を刊行。